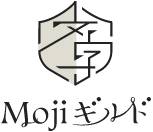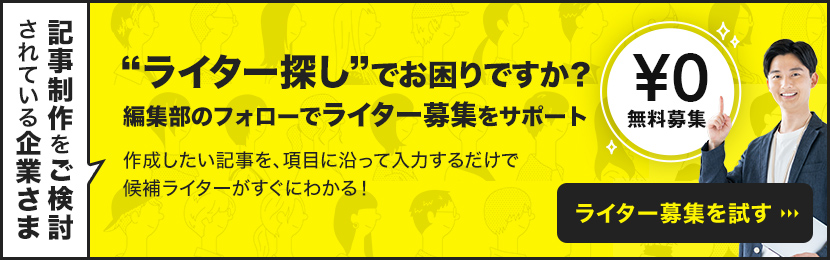天国から地獄!筆者の記事が炎上するまで
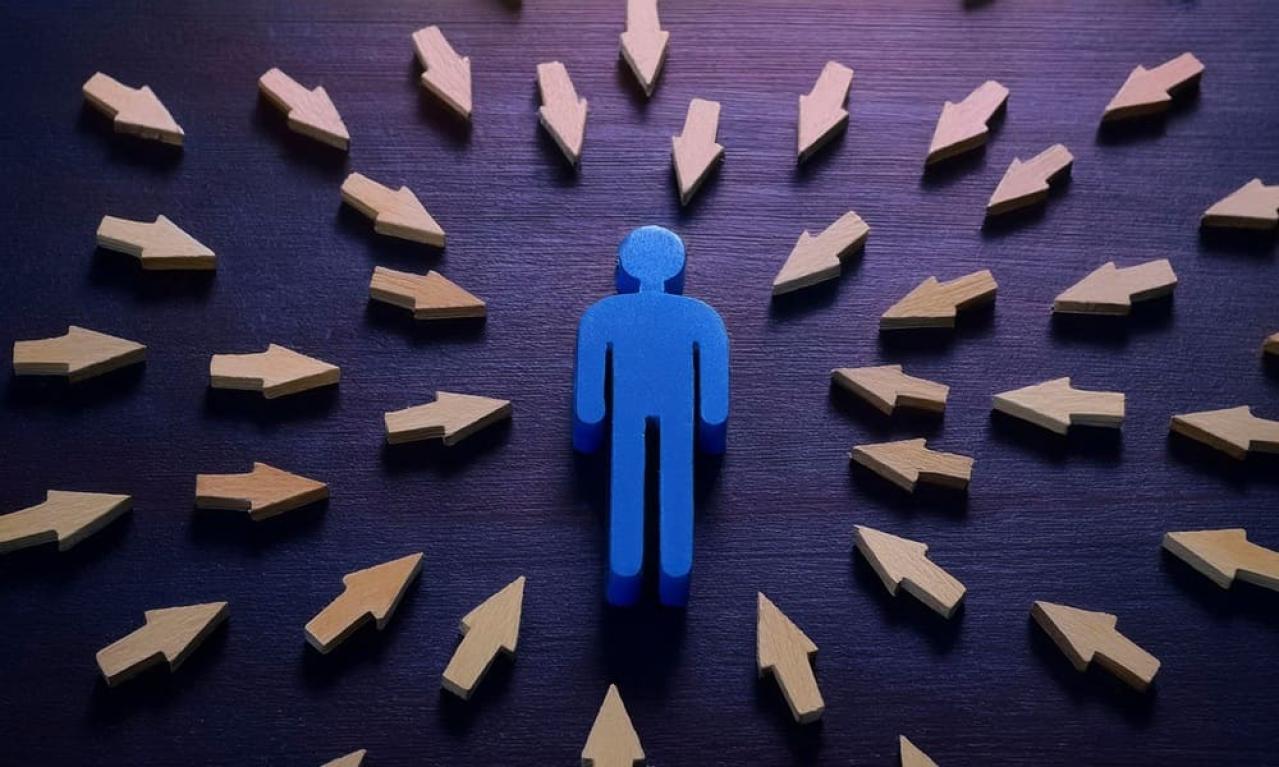
まずは、筆者が体験した炎上事件について、時系列に振り返ります。
「やっと掴んだチャンス!」はじめての記名記事に舞い上がる
ライター業を始めて半年を迎えた頃、当時所属していた編集プロダクションより「記名記事を書いてみないか?」とお誘いを受けました。駆け出しのライターであれば理解いただけるでしょう。
記名記事は、案件獲得時のアピール材料として利用できるため、喉から手が出るほどありがたいものです。当時の筆者も同じ考えで、心の中でガッツポーズをした記憶があります。「やっと掴んだチャンス!」をものにするぞと意気込んで執筆に取り掛かりました。
渡された構成案と、見過ごした危険信号
記名記事の内容は、歴史上の出来事について、面白おかしくまとめるものでした。構成は別のディレクターが作成しており、私はその内容に従って調査と執筆を担当します。
構成内にて、いくつか参考とするWebサイトも掲載されており、各記事の内容も取り入れながら執筆を進めました。「構成案で示されているから問題ないか」と思い、各Webサイトへの確認が必要かどうかも考えずに初稿を作成し納品しました。
急激に伸びるコメントと犯人探し
無事に納品が完了し、クライアントより掲載予定日を知らされました。「いよいよ記名記事が公開される」と思い、その日は朝からソワソワしていたことを覚えています。
記名記事が公開されるや否や、思いのほかコメントが殺到しました。最初は「多くのPVが稼げそうだ!」と思って喜んでいたのですが、時間が経つにつれて雲行きが怪しくなっていったのです。
「そんな事実はない!」「この記事はパクリだ!」といった投稿も増え、あれよあれよと炎上状態になっていきました。しまいには「この筆者は誰だ!」という人も現れ、当時使用していたSNSのアカウントが特定され、そちらでもクレームが投稿されるようになったのです。
今だから言える「あの時こうしておけば…」

炎上当初は冷静さを欠き、嵐が過ぎ去ることばかりを考えていたものの、今なら冷静に当時の失敗を分析できます。あの炎上は、決して事故ではなく、以下のような筆者の油断が招いた結果だったと反省しています。
「構成案は絶対」という思い込み
最大の失敗は、「構成案は絶対」という思い込みを持っていたことです。クライアントの意向を汲むことは当然ではあるものの、ディレクターも気づいていないリスクがあれば、プロのライターとして、より良い方向へ導く「提案」をするべきでした。
参考にすべきWebサイトだけでなく、公的な資料などからファクトチェックを行い、より精度の高い構成案を共有できていれば、炎上は避けられたでしょう。
「知らなかった」では済まされない引用・参照のルール
炎上した記事の中で、批判が集中したのがマニアックなサイトを参考に執筆した部分でした。
筆者はこの時、引用元を明記せずに執筆してしまったのですが、偶然、この点が読者の知るところとなり、サイトの持ち主の知るところとなったのです。
先方からは記事を掲載しているクライアントに連絡が入り、結果的に記事の訂正と謝罪文を掲載することを条件に許していただけました。「知らなかった」では済まされないルールがあるのだと、深く体感した出来事でした。
「自分は大丈夫」と軽視した”身バレ”対策
初の記名記事だからといって、本名を連想させる名前を使用していたのも間違いでした。万が一、炎上してしまったとしても、身バレにつながらないライター名を使用していれば、SNSアカウントの特定まではされません。
どのようなライター名にするかの判断は難しいところではありますが、ライターを始めたばかりの頃は、安易に本名で活動するのは避けたほうがいいかもしれません。「自分は大丈夫」と思わずに、ライター業の勘所がわかるまでは、本名や本名から連想できるような名前は利用しない方がいいでしょう。
炎上中、どう過ごしていたか
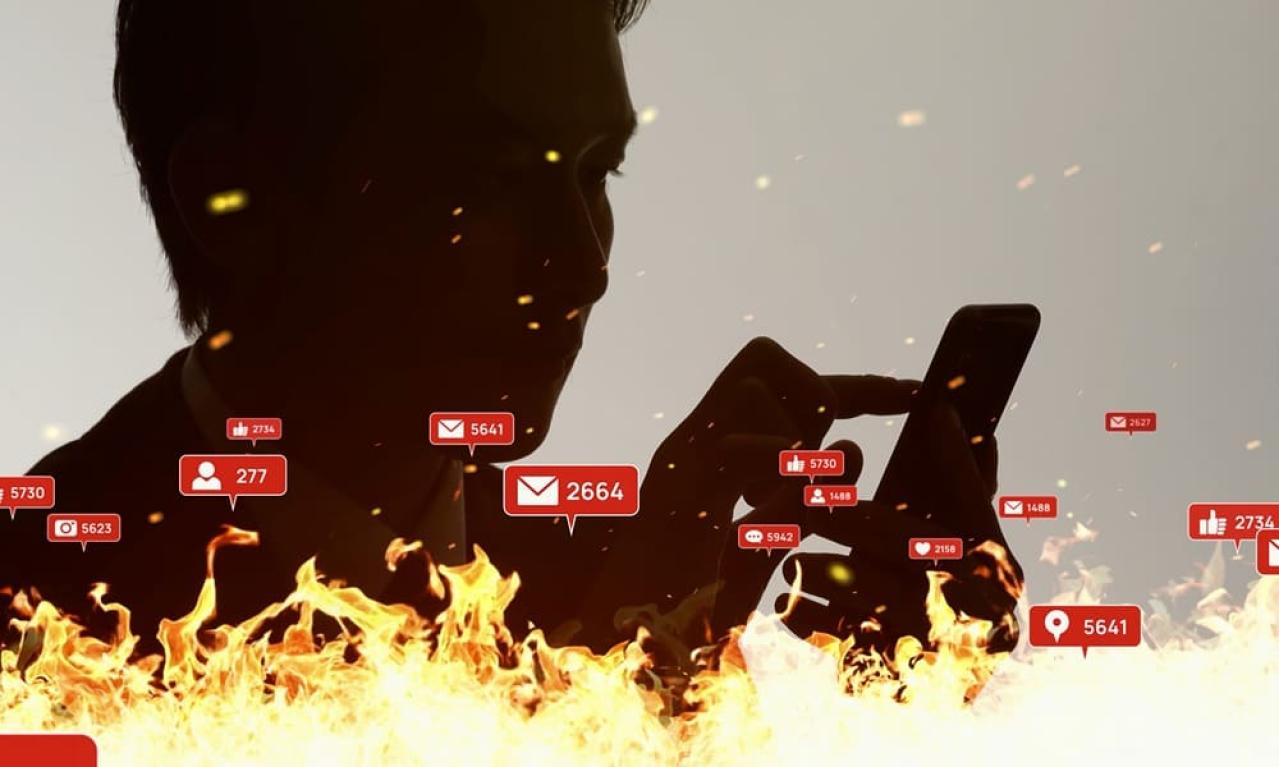
実際に炎上が発生して数日の間、「誰かが乗り込んでくるのでは?」「電話が鳴りやまなくなるのでは?」といった不安を抱えて過ごしていました。それでも以下の行動をとったことで、冷静さを取り戻せました。
まずは報連相。ディレクターに事実を報告
コメントの投稿が荒れ始めたタイミングで、すぐにディレクターに報告しました。責任問題になるかもしれないと恐る恐る連絡をとったのですが、「巻き込んでしまい申し訳ありません。すぐに対応を協議します」といって、クライアントとの調整など迅速に動いてくれました。
もし、筆者が隠ぺいしたり、ひとりでなんとかしようと考えていたら、事態は収まるどころか悪化していたかもしれません。
どのような状況であれ、ディレクターへの「報連相」は自分を守るための生命線であることを忘れないようにしましょう。
SNSにて謝罪文の掲載
ディレクターに報告したあとは、指示に従い行動することとなりました。出来事は逐次報告し、対処すべきことはすぐに実行するという状況でした。
SNSのアカウントが特定された場合もすぐに相談し、「謝罪文を掲載しよう」という話になりました。
文面もディレクターと相談し、記事のどの部分に配慮が欠けていたか、筆者の認識不足が多くの人を不快にさせたことを文章にしました。
なかには「火に油を注ぐだけ」「売名行為だ」といった批判もありましたが、「謝罪できるだけマシ」「次に活かせばいい」という声もあり、沈静化するきっかけとなったと感じています。
先輩ライターに相談したら意外な返答が
炎上当初、別の案件でお世話になっていた先輩ライターがいました。SNSでアカウントが特定されたこともあり、迷惑をかけるかもしれないと思って謝罪に伺いました。すると先輩ライターからは意外な返答が返ってきたのです。
「これで一人前ですね」
その先輩ライターも炎上を経験していました。詳しく話を聞くと、筆者よりもひどい状況だったようです。それでも彼は自分を強く持ち、ライター業を続けています。
その姿を見て、「これもひとつの経験なんだ」と感じることができました。
嵐が過ぎて気づいたこと

まるで世界中から非難されているように感じた炎上も、いつしか鎮火していきます。特定されたSNSアカウントにも、今ではクレームを言ってくる人はいません。嵐が過ぎ去ったからこそ気づいたことは次のような内容です。
直接のクレームはまずない
あれだけコメントやSNSで叩かれたにもかかわらず、筆者のメールアドレスや仕事用の連絡先に、直接クレームを送ってきた人はひとりもいませんでした。
あれほど筆者を敵視していた人たちも、わざわざ時間と手間をかけてまで、個人を攻撃してくることは稀なのでしょう。
先輩ライターからも、「直接言ってくる人はほとんどいないよ」と教わり、「ネット上の騒ぎと、現実の自分は別なんだ」という気づきから、筆者は少しだけ強くなれました。
明けない夜はない
炎上のピークは、最初の数日間だけでした。ディレクターの対応や、SNS上での謝罪の効果もあったのか、1〜2週間も経てば炎上騒ぎなど誰も覚えていないかのように、ネットは静かになっていました。
渦中にいると、苦しみが永遠に続くように感じるかもしれません。でも、大丈夫です。明けない夜はありません。ネットの炎は、あなたが思うよりずっと早く燃え尽きて、忘れ去られていくものです。
過度に炎上を恐れず、あなたの言葉を紡いでいこう

執筆した記事の炎上は、できれば避けたい出来事です。ただし、炎上を恐れるあまり、挑戦をやめてしまうのはもったいないです。
確かに筆者の記事は炎上しました。「ライターとして失格」という厳しいコメントもいただきました。それでも炎上の経験を糧として改善に取り組み、挑戦を続けた結果、現在の成果につながったと確信しています。
大切なのは過度に炎上を恐れるのではなく、リスクを知って備えることです。仮に炎上してしまっても、適切に対処すれば大きなケガは防げます。
失敗しても、大丈夫です。前を向いて、あなたの言葉を紡いでいってください。
この記事を書いたライター
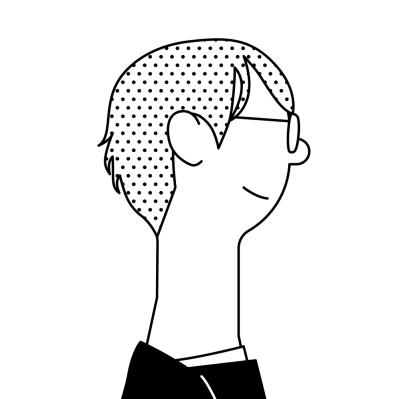
中島正雄
ITエンジニア、速読インストラクター、パーソナルトレーナーなど、異色の経歴を持つライター。得意ジャンルはIT・システム開発関連、製造業などのビジネス系や、転職サイトでの企業紹介記事や、Webメディアでの専門家取材記事など。クライアント...