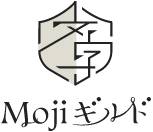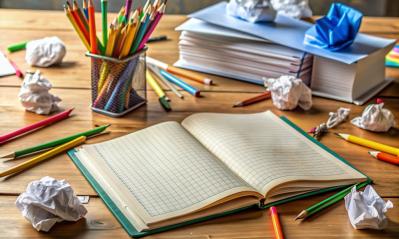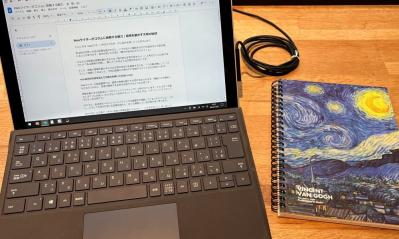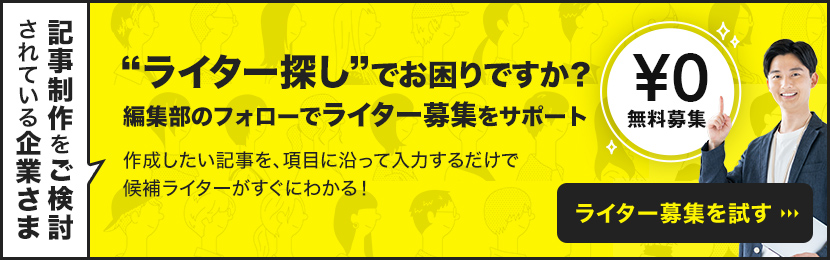ドキュメンタリー番組のナレーションを参考にした理由

まずは私が、なぜナレーションをライティングの参考にしたか、ご説明しましょう。
単調で平坦な文章に、もどかしさを感じていた
Webライターとして活動を始めた当初、私はライティングで悩んでいました。言いたいことを書いているのに、どこか単調で、読み返しても何が良くて悪いのか自分で判断できず、毎回モヤモヤしたまま記事を提出していたのです。
そこで私は、Webライティングについて書かれた専門書やWebサイトを読み、ヒントになることを探しました。
いい文章とは、口に出して読んでもいい文章?
Webライティングの専門書やWebサイトを読んでいた時、気になるアドバイスがよく目に留まりました。それは「いい文章とは、口に出しても違和感がない文章」「チェックする時は口に出して読む」というものでした。
実践してみると、確かに文章の違和感に気づきやすく、テンポの悪さや誤字脱字もわかるようになったのです。
「声に出すことを前提に作られた文章を参考にすれば、もっと勉強になるのでは?」そう思った私は、お手本になりそうな話すための文章を探し始めました。
口に出して読む文章を追っていたら、ナレーションにたどり着いた
そうしてたどり着いたのが、ドキュメンタリー番組のナレーションでした。ナレーションは、感情を込めて演じる芝居のセリフとは違い、基本的には情報を正確かつ理解しやすいように伝えることが目的です。
耳で聞く視聴者にも内容が伝わるように書かれており、テンポの良さも考慮されています。説明や解説をする内容も多いため、Webライティングに取り入れやすく、非常に参考にできると思ったのです。
私はYouTubeでドキュメンタリー番組のナレーションを探し、AIの自動文字起こし機能を使って文章を抽出し、構成や言い回しを研究しました。
ナレーション文章の特徴と参考にした動画
私が参考にしたのは、主に3つのYouTubeチャンネルです。
- ナショナル ジオグラフィック TV:https://www.youtube.com/@natgeotv_jp
- ディスカバリーチャンネル:https://www.youtube.com/@DiscoveryJapan
- 情熱大陸 公式チャンネル:https://www.youtube.com/@jounetsu
「ナショナル ジオグラフィック TV」と「ディスカバリーチャンネル」は、専門的なジャンルの解説・紹介系の動画が中心。専門的な内容を視聴者にもわかりやすく説明する動画は、ライティングの参考になりました。
「情熱大陸 公式チャンネル」は、ストーリー性のあるナレーションが魅力です。視聴者の心を引き込む言葉選びや構成は、「読ませる力」のヒントになりました。
他にも「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」「歴史探偵」といったTV番組や、ニュース番組の特集なども参考にしました。こうした番組のナレーションを参考にし、自分の文章にテンポの良さとわかりやすさを取り入れていったのです。
※ナショナル ジオグラフィック TVとディスカバリーチャンネルは、日本語ナレーションの動画は全体の一部です。
ナレーション的手法を取り入れて得られた気づきと効果

ドキュメンタリー番組のナレーションを参考にする中で、私の文章にはいくつかの変化が生まれました。ここからは、実際に取り入れて感じた気づきや効果をご紹介します。ライティングに取り入れる際のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
テンポの良さで読みやすくなった
ナレーションを参考にしたことで、文章の単調さが減り、テンポの良い文体へと変化しました。ナレーションは「耳で聞くこと」を前提にしているため、語尾のバリエーションやリズムに配慮がなされ、聞き手を飽きさせない工夫が詰まっています。
例えば「マチュピチュは太古から伝わる神秘の地です」という一文よりも、「太古から伝わる神秘の地、マチュピチュ」と語順を変えた方が、印象に残りやすくなるでしょう。
この特徴をWebライティングに応用することで、語尾の繰り返しや読みにくさを避けやすくなり、読者にストレスを与えにくい文章にできました。
リード文にナレーション的手法を導入できた
Web記事において重要なリード文でも、ナレーションの手法を活かせました。ドキュメンタリー動画にも、冒頭に視聴者の関心を引きつける語り出しがあります。これが、Webライティングにおけるリード文とよく似ていたのです。
私が参考にしたナレーションでは、多くが次のような構成になっていました。
①テーマ・問題提起(いつ・どこで・何の話か)
②対象の紹介(サービス・商品・題材など)
③詳細な説明(具体的な特徴や内容)
④特別な要素(驚きの事実や独自性)(例:驚きの~とは!?)
⑤まとめ
この構成は、読者の興味を引きつけ、スムーズに本文へ導くうえで非常に役立ちます。記事のリード文を書く際にこの型を意識することで、内容を整理でき、読者を引き込む文章を書きやすくなるでしょう。
ストーリー性と情報の整理を両立できた
ナレーションの手法を取り入れることで、ストーリー性と情報の整理を両立できました。
ナレーションは視聴者にわかりやすく伝えるため、ストーリー性で面白さや共感を作りつつ、重要な情報を順序よく説明しています。
この特徴を参考に、私はWebライティングでも具体例の提示により意識を向けるようになりました。具体例があるかないかで、読者の共感度や理解度が大きく変わることを実感したためです。
例えば、ベッドについて紹介する記事を書くとします。
「高齢者にとって、適切な寝具選びは重要です」といった一般的な説明だけでは、読者は具体的な状況をイメージしにくいでしょう。
しかし「高齢になると、布団からの立ち上がりがつらくなる──」といった読者の悩みに寄り添いながら、「この低めのベッドを利用することで、高齢者が寝起きする負担を減らせるでしょう」と具体的に示せば、読者が状況をイメージしやすくなり共感が深まります。
ナレーションの手法を活かすことで、ストーリー性と情報の整理を両立し、具体例を交えることで読者にとってわかりやすく説得力のある文章が書けるようになりました。
書くことが楽しくなった
ナレーション的な手法を取り入れたことで、文章を書くのが以前より楽しくなりました。なぜなら、言葉の流れや場面の描写を意識することで、頭の中に情景が浮かびやすくなり、内容を整理しながら書けるようになったからです。執筆スピードも向上しました。
具体的には、専門的な知識を伝える場面では「ディスカバリーチャンネル風」、活動や人物紹介では「情熱大陸風」といったスタイルを意識するようになりました。
あらかじめ完成イメージがあることで、構成の方向性や表現の基準が明確になり、「どんな文章に仕上げたいか」の判断がしやすくなったのです。
その結果、迷いなく書けるようになり、文章を書くこと自体がいっそう楽しく感じられるようになりました。
取り入れる際の注意点

ライティングにナレーション的手法を用いることは、文章に深みとリズムをもたらす効果的な方法です。しかし、その導入には、いくつかの注意点があります。
ここでは、ナレーションをライティングの参考にする際の注意点を紹介します。
テンポがおかしくなる場合がある
ナレーション的な文章は耳で聞いたときに心地よいテンポを意識して作られていますが、そのままWeb文章に転用すると、読者にとって不自然に感じられる場合があります。
ナレーションでは「間」を取るために効果的だった句読点が、文章で見ると不要なものに感じられるのです。
例えば以下の例をご覧ください。
- ナレーション
「新たに開発されたシステムは、多くの企業に導入され、その効率化と生産性の向上に、大きく貢献しています」 - Webライティング
「新たに開発されたシステムは、多くの企業に導入され、その効率化と生産性の向上に大きく貢献しています」
このように、ナレーションでは「生産性の向上に」と「大きく貢献しています」の間に読点を入れて間を取り、リズムを作っています。しかし、Web記事ではこの読点がリズムを乱し、読みづらくしているのです。
ナレーションで使われる句読点の位置や数は、Webライティングで必ずしも適切とは限らないため、読み手の視点で調整することが大切です。
耳に優しくても、目で読むと違和感がある
ドキュメンタリー番組のナレーションには、「だ・である」調で語られていたり問いかけが多かったりする文章があります。しかし、Webライティングにおいて、ナレーションの表現をそのまま使うと、読者に違和感を与えてしまう場合があるでしょう。
例えば「本当にそうだろうか?」のような問いかけは、ナレーションでは間を持たせる効果があります。しかし、Web記事では読者にとって唐突に感じられ、内容の理解を妨げることがあるのです。
ナレーションで使われる問いかけは、映像や声の間合いで視聴者の注意を引くことができますが、Web記事では読みづらくなります。そのため、Webライティングでは読者の読みやすさを最優先に、文体や表現を適切に調整することが重要です。
情緒的になりすぎる
Webライティングでは、読者が求めているものは「情報」です。情緒的な表現や言い回しにこだわりすぎると、かえって伝えるべき内容がぼやけてしまいます。
例えば、「まるで奇跡のように、静かに幕を開けたプロジェクト──」といった導入は、Web記事では回りくどく感じられるかもしれません。
あくまで「わかりやすさ」が最優先。ナレーション的な手法は、読みやすくするためのスパイス程度にとどめ、主役は明確な情報であるべきです。
読者にとって心地よい文章とは、感情に訴えるものではなく、ストレスなく知りたい情報にたどり着ける構成に沿ったものです。
まとめ
ここまで、ドキュメンタリー番組のナレーションを参考にした文章表現の工夫について紹介してきました。
ナレーションならではのリズムや言葉選びを活かすことで、文章のテンポが良くなり、読みやすさが向上します。特にリード文や具体例を用いた説明に取り入れると、より効果的です。
ぜひ実践して、書くことを楽しみながら、読者にも伝わりやすい記事を目指しましょう。
この記事を書いたライター
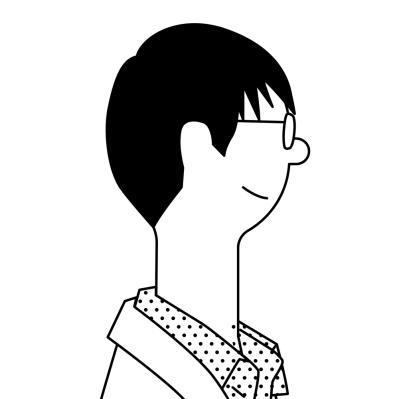
水木ゆう
フリーランスのWebライターです。自身でネットショップを運営していた際に、ブログを執筆したことでライティングに興味を持ちました。得意なジャンルは「歴史」「アニメ」「ゲーム」「観光」などです。また、ナレーターの勉強をしていた経験があ...